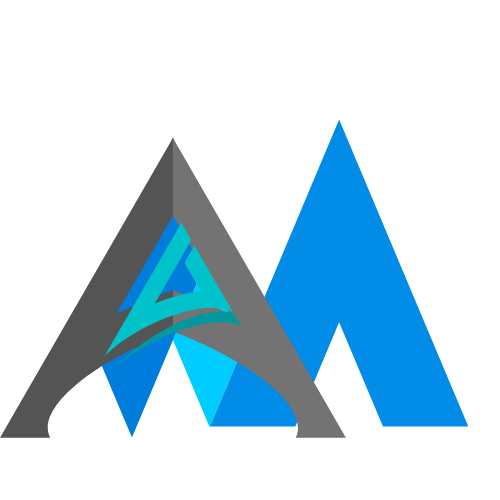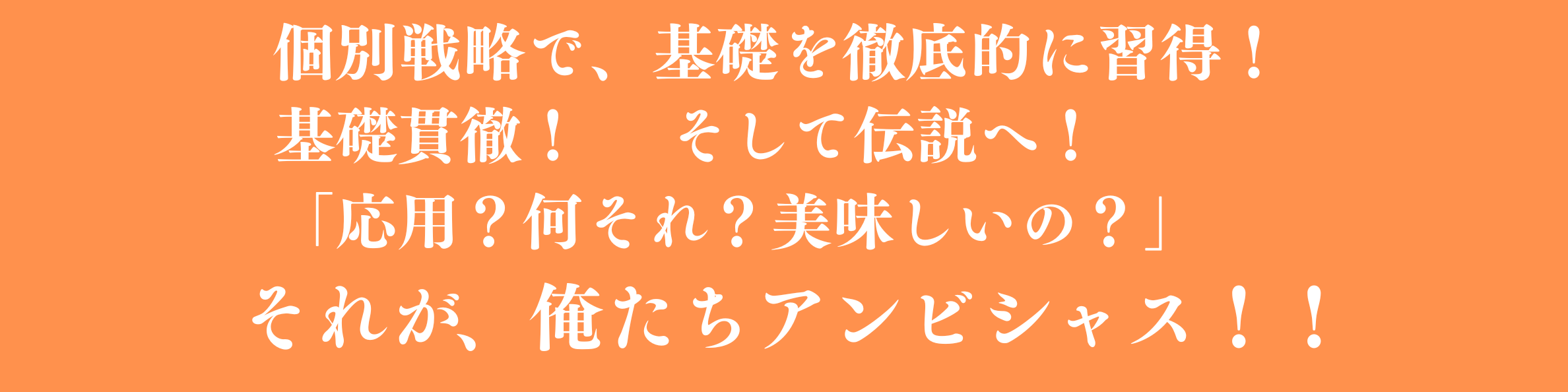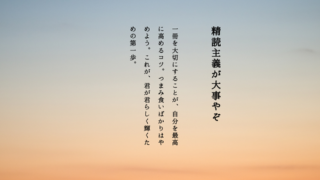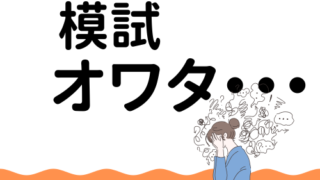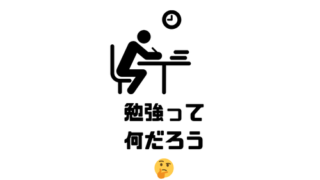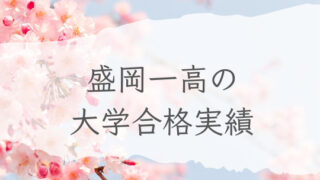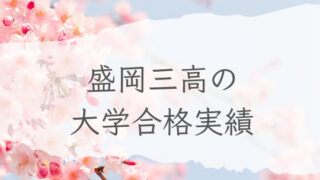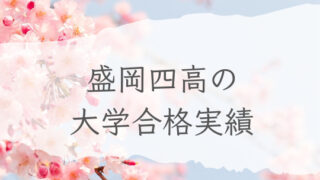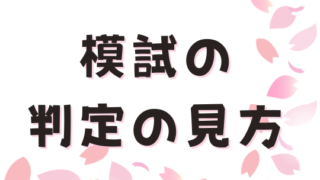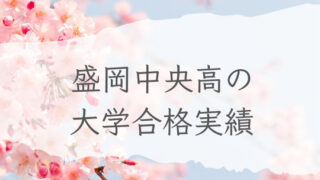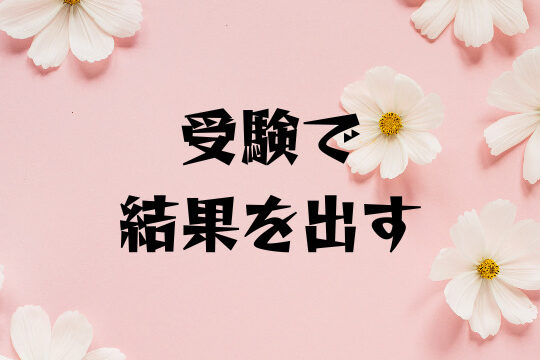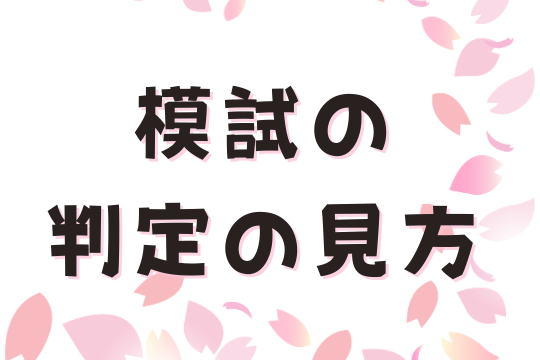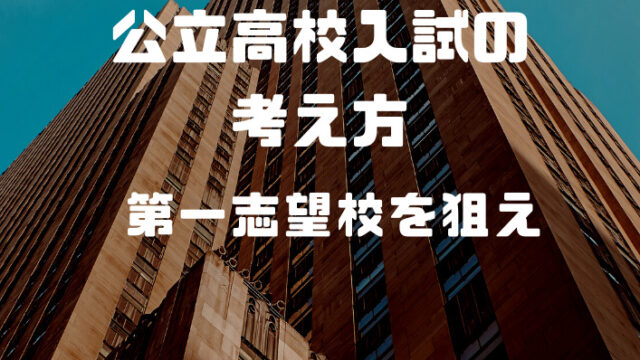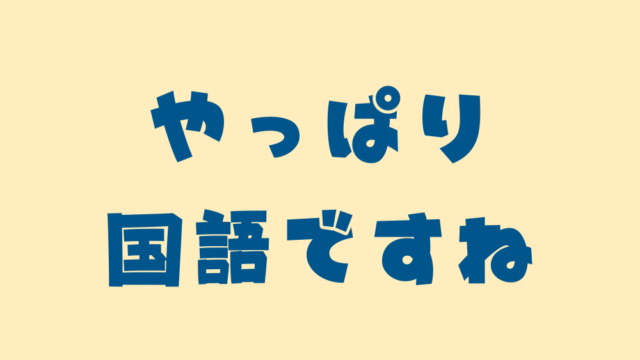先日、国立大学の教授と2人で話す機会があった。
その中で出た話題を少しまとめて、今日から3回に分けてアップしていきたいと思う。
今日は、その1回目だ。時間があるときに呼んでいただけると幸いである。
はじめに
「うちの子、大学に入ったはずなのに、高校の勉強をまたやっているらしい……」
そんな声が、最近保護者の方からも聞かれるようになった。
大学とは本来、専門分野の学問を深く掘り下げ、自分の関心を研究へと広げていく場のはず。
しかし、現実には、一部の大学で「高校レベルの数学や英語の補習」が行われている。
驚くべきことに、これは国立大学も例外ではないのだ。
つまり、大学生なのに高校のやり直しから始めなければならない状況が増えているということだ。
これは単なる一部の大学の特殊事情ではなく、日本全体の高等教育が抱える「構造的な問題」を映し出している。
今回は、その背景と意味を整理しながら、保護者としてどう考えるべきかを伝えてみたいと思う。
推薦入試組と一般入試組の逆転現象
かつて「学力エリート」といえば、一般入試を突破した学生だった。
一方で、推薦やAO入試で入学する学生は「内申点や活動実績はあるけれど、学力面では一般入試組より少し劣る」というイメージがあった。
ところが今、現場の大学教授から聞かれる声は真逆なのだ。
「推薦入試で入った学生の方が、基礎学力がしっかりしていて安心感がある」
「一般入試で入ってきた学生の中には、かつてなら到底入学できなかった学力層が混ざっている」
推薦入試組は、高校生活をきちんと積み上げてきた「まじめでコツコツ型」。
一方、一般入試組は「短期決戦型」なのだが、受験人口が減った結果、入試の難度そのものが下がり、合格ラインも大きく下がってしまった。
そうだ。
かつてなら門前払いだった学力層も、大学に入学できるようになっているんだ。
これは、衝撃的だが、紛れも無い事実なのだ。
背景にある「少子化と定員維持」の矛盾
ではなぜこのような逆転現象が起きているのだろうか。
最大の原因は、「少子化なのに大学の定員がそこまでは減っていないこと」だ。
18歳人口はピークの半分以下になった。
しかし大学の数も定員も、バブル期の拡大路線のまま。
結果として、合格ラインを下げてでも「席を埋めなければならない」。
本来なら、人口減少に合わせて大学の数や定員をスリム化すべきだった。
しかし、それができないまま「門を広げて定員を埋める」方向に走ったため、
大学の入り口が広がりすぎてしまったと言える。
「高校の延長」と化す大学
こうして学力層の幅が広がった結果、大学は「新入生の基礎学力のバラつき」という課題を抱えることになった。
すると大学側は、以下の対応策を講じざるを得なかった。
数学や英語の基礎をやり直す「リメディアル教育(補習)」を導入。
研究に入る前に「高校レベル」の穴を埋める必要がある。
中には「高校の先生を非常勤で呼んで補習をする」という大学すらある。
これではまるで「高校の延長」だ。
本来の大学教育(専門分野の学問探究)に時間と労力を割く前に、足場づくりから始めなければならない。
結果として、大学の教育水準そのものが押し下げられてしまっているのだ。
その影響は優秀層にも及ぶ
さらに深刻なのは、優秀な学生への悪影響だ。
大学の授業は「学力下位層に合わせた進度」になりがちだ。
すると本来ならもっと先へ進める学生も、基礎に足止めされてしまう。
大学が「研究への挑戦」より「高校内容の補修」に追われる状況は、
優秀層の伸びを削ぐことにもなる。
つまり「大学の高校化」は、単に下位層の救済だけでなく、上位層の可能性まで奪うリスクを孕んでいるということだ。
親としての視点
ここで大切なのは、「大学の名前」に惑わされないことだ。
同じ名前の大学でも、昔と比べて入学の難度は大きく下がっている
入学者の層も広がり、補習が当たり前になっている
という現実があるからだ。
つまり「偏差値」や「ブランド」で安心するのではなく、
その大学がどのような教育方針を持ち、
どのようなサポート体制を整えているのか、
そして子どもがそこで何を学び、どう成長できるのか
を冷静に見極めることが、これからの時代の保護者に求められる姿勢だと思う。
もちろん、学生本人にも求められている。まあ、これは当たり前だが。
まとめ
大学で高校内容の補習が行われるようになったのは、少子化と定員維持という矛盾が生み出した構造的な問題だ。
推薦入試組の方がむしろ学力が安定しているという逆転現象も、決して偶然ではない。
そしてこの現象は、大学教育そのものを「高校の延長」にしてしまう危険性をはらんでいる。
本来なら「学問を探究する場」であるはずの大学が、「高校のやり直しの場」に変わってしまえば、その価値は大きく損なわれてしまう。
保護者としては、大学名や偏差値だけで判断するのではなく、
「この大学でわが子は何を学べるのか」 という視点で選び、支えることが何より重要になって来るだろう。
明日は、第2回をアップしたいと思う。