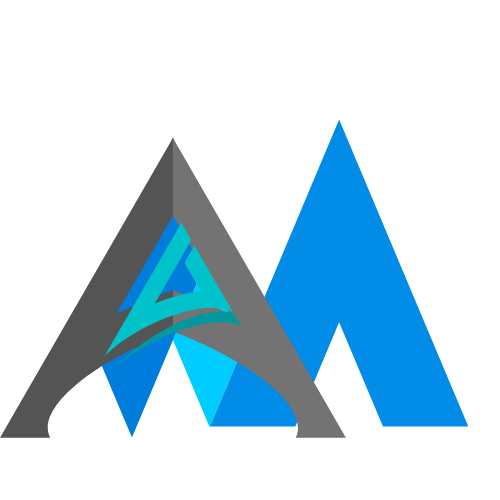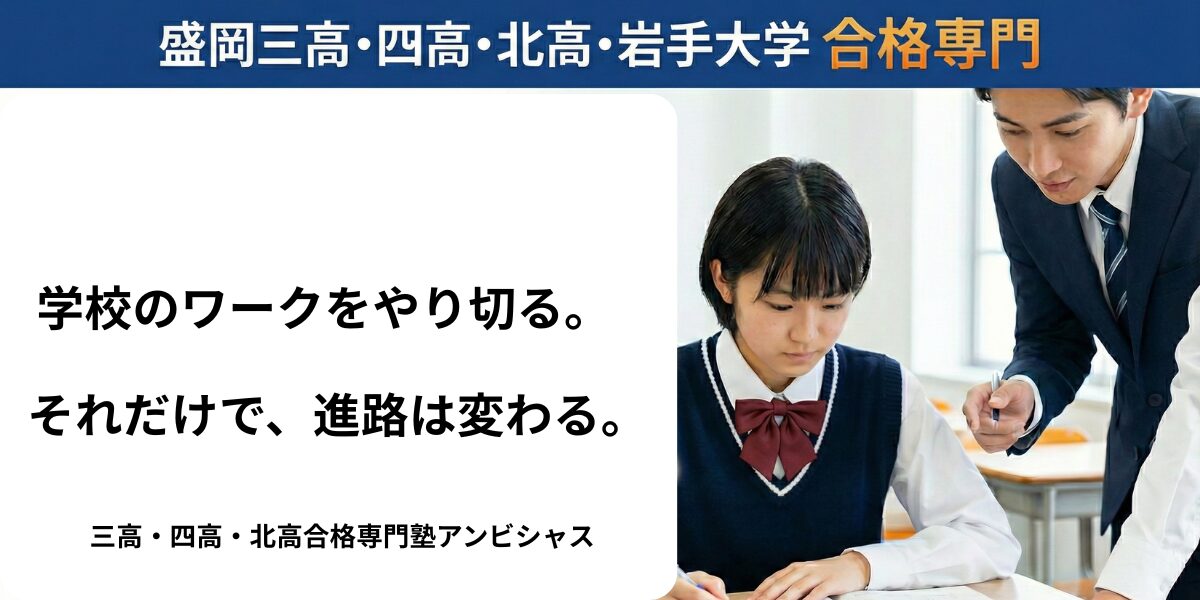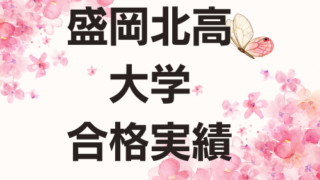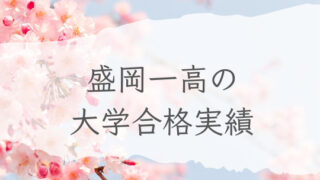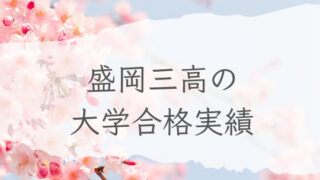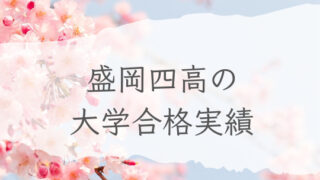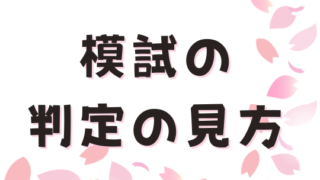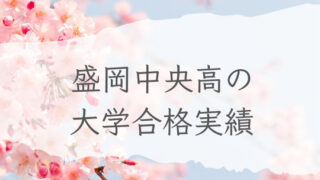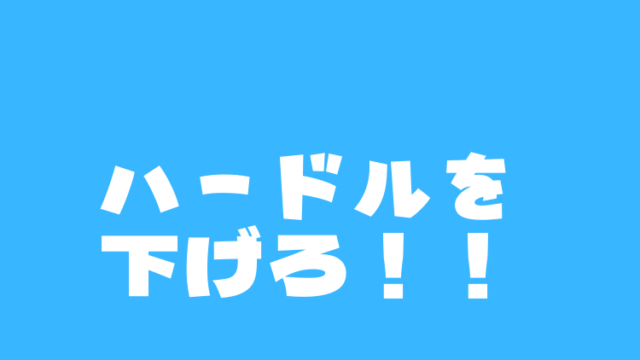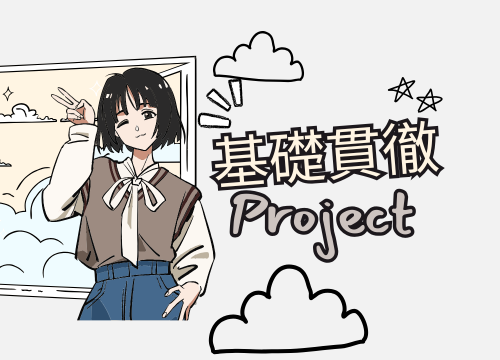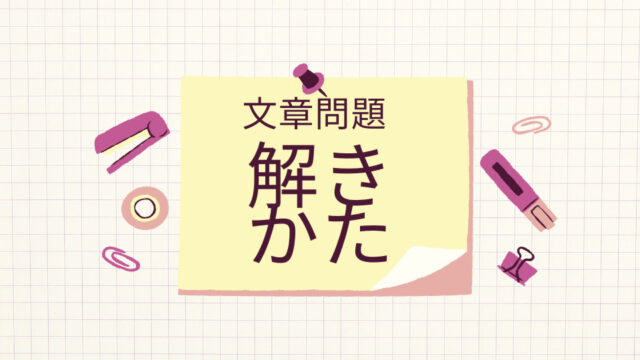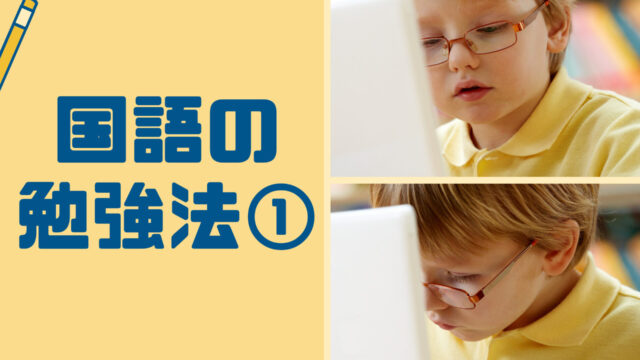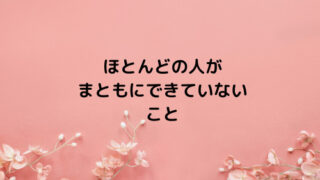英語が現行の教科書になって起きたこと
それは、学校の英語のテストにおける平均点の大幅な下落だ。
要は、点数が取れる子と取れない子に、はっきりと分かれてしまったということである。
もちろん、教科書の難化がその背景にあることは確かだ。
しかし、それ以前の問題もある。
それは、国語が苦手な子が多いということだ。
国語の短文も長文も理解できない子が増えているのである。
そうだ。国語と英語には密接な関係がある。
この関係性は、特に、高校以降に顕著となってくる。
つまり、「国語ができないと英語もできない」のだ。
「国語ができない」とは、「国語に対して鈍感だ」と言い換えることができる。
一つ、例を挙げよう。
「は」と「が」の使い分けについて意識できているかどうかで、適切な表現なのかどうかが変わることがある。
「Aくん、勉強に取り組む姿勢はすごく良いね。」と
「Aくん、勉強に取り組む姿勢がすごく良いね。」とでは、だいぶ意味合いが違ってくる。
取り組む姿勢「は」だと、それ以外はダメなのか?という意味合いになる。
こういう部分に、普段から敏感になる必要があるのだ。
そうでなければ、英語のSVOCなんて理解できるはずがない。
要は、自分が意図した内容を正確に伝える、表現することができる能力が国語力と言うこともできるだろう。
もう一つ例を挙げよう。接続詞の問題だ。
逆説の「しかし」と添加の「そして」の使い分けが曖昧なら、英語の「but」と「and」も曖昧になってしまう。
最近は、国語で接続詞の選択問題を間違える子が大幅に増えたと感じる。このような子は、例外なく、英語の長文も苦手なのだ。
以上のことは、文章の論理構造を把握することにつながってくる。
日本人の母語である国語で文章の論理構造を把握することができなければ、
外国語である英語で主語と述語、目的語の関係や接続詞の機能を理解できるはずがない。
そして、この国語は、小学校修了までの12年間で大きく差がついてしまっているのだ。
英語を集中的に勉強しても点数が上がらないケースの多くは、母語である国語力に問題があるのだ。
ここをきちんと認識しておかないといけない。