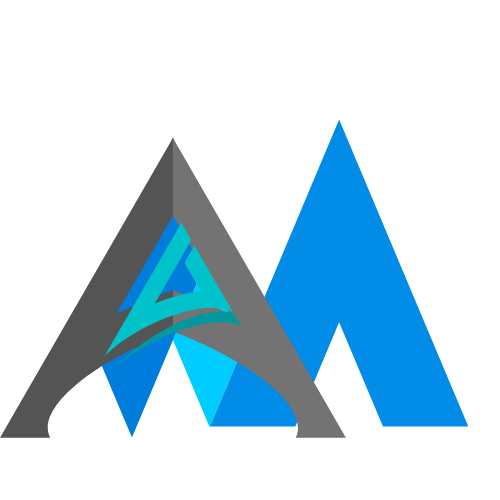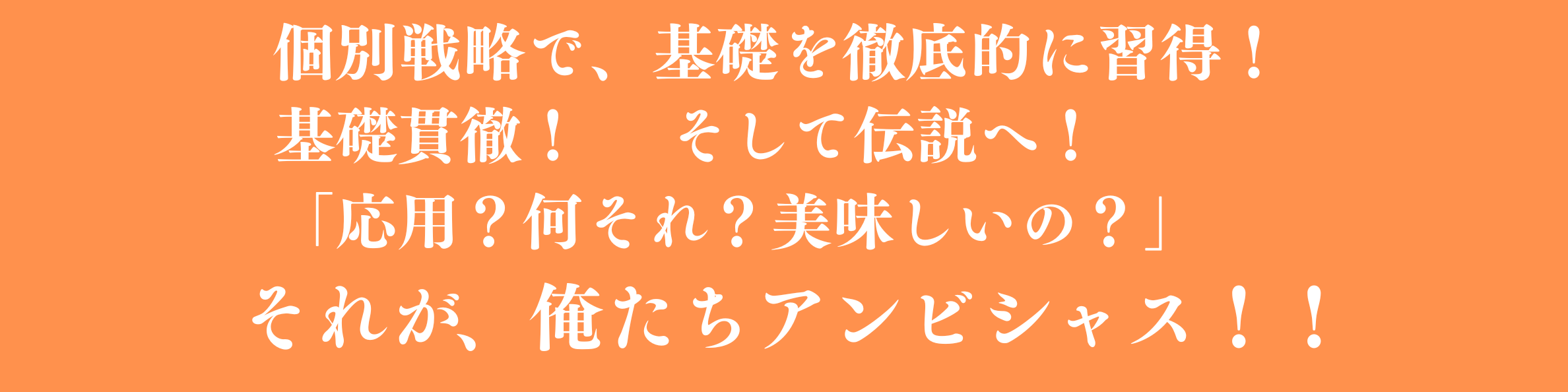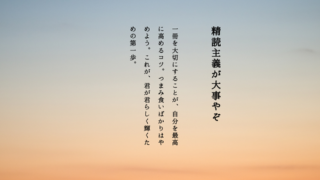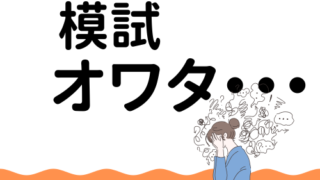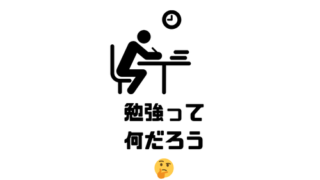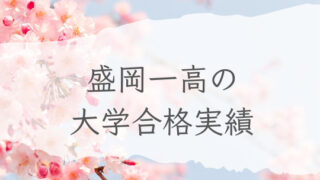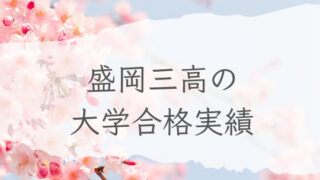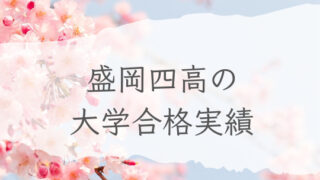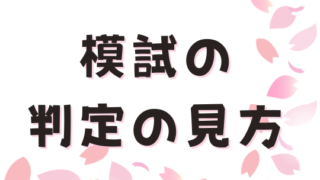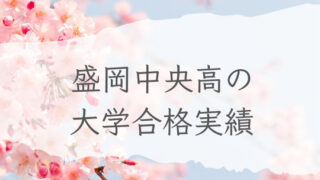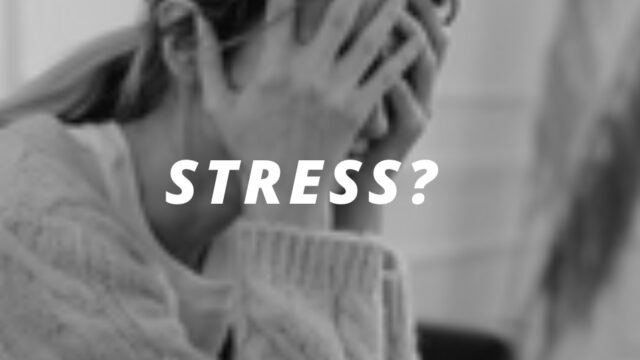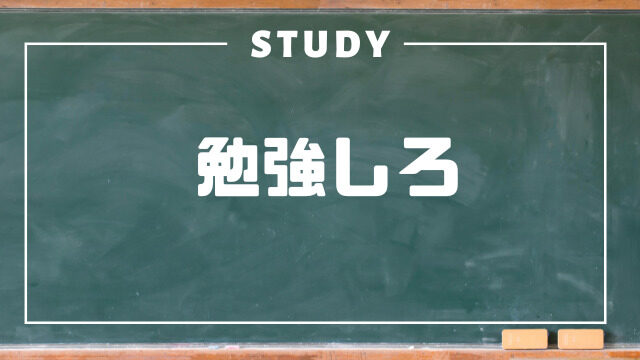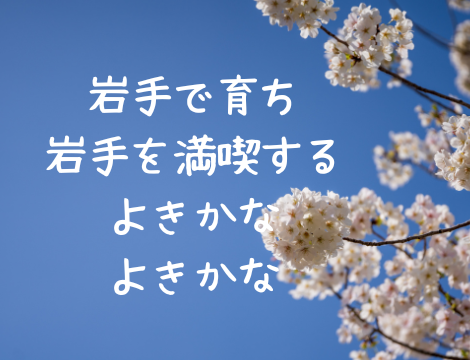はじめに
大学4年生にとって「卒業論文(卒論)」は、学びの集大成である。
数万字にわたる文章を自ら構想し、調査・研究し、まとめ上げる作業は、
社会に出る前に「自分で考え、表現する力」を鍛える最後の場でもある。
ところが近年、大学の現場からこんな声が聞かれるようになった
「卒論を書けない学生が増えている」
「テーマはあるのに、文章としてまとめられない」
「指導しても、段落を組み立てられない」
単に「文章が下手」というレベルではなく、「文章を組み立てること自体ができない」学生が増えている。
これは大学教育の危機であると同時に、家庭教育や社会全体が直面する問題でもある。
なぜ「卒論が書けない」のか?
学生が卒論でつまずく原因を、大学の先生方は以下のように指摘している。
読解力の不足
文章を読んでも内容を正確に理解できず、要点をつかむのが難しい。
→ 参考文献を読んでも「何が書いてあるのか」が整理することができない。
論理構成力の欠如
文章の筋道を立てることができない。
→ 「序論・本論・結論」という基本の型すら組み立てることができない。
表現力の未熟さ
自分の考えを適切な言葉にできない。
→ 単語を並べるだけで文章にならない。
つまり「知識が足りない」のではなく、知識を整理して文章化する力が足りないということだ。
なぜこんなことになったのか?
複数の原因が考えられる。
1. 入試が「書かなくても受かる」方式になっている
大学入試の主流はマークシート。
選択肢を選べば合格できる。
自分で文章を書く力は問われない。
そのため「高校3年間、一度もまとまった文章を書かないまま大学に入学する」ケースが普通にある。
2. SNS・短文文化の影響
現代の若者は、文章を書くといってもLINEやSNSが中心。
1行や短文で意思疎通が成立してしまう。
絵文字やスタンプで感情を表現する習慣。
結果として「長文を書く体力」が育たないのでは無いか?と指摘されている。
3. 大学の大衆化
昔の大学は「研究者志向の学生が集まる場」だった。
しかし今は、大学進学率が5割を超え、「ほぼ誰でも大学へ行ける時代」になった。
→ 結果、「文章を書く習慣のない層」まで大学生に含まれることになった。
卒論が書けないことの意味
卒論が書けないというのは、単に「文章が下手」という問題ではない。
それは、 「考える力」そのものの不足を意味します。
文章を書くには、情報を整理し、筋道を立て、表現する必要がある。
書けないということは、「考えをまとめ、他者に伝える力」が欠けているということだ。
これは社会人生活にも直結する。
→ 企画書が書けない、報告書が書けない、顧客に説明できないということが起こり得るからだ。
つまり、「卒論が書けない学生」とは、「社会で必要な基本スキルを持たない学生」でもあるのだ。
保護者ができること
では、保護者は子どもの文章力低下にどう向き合えばよいのだろうか?
1. 「説明させる」習慣を持つ
読んだ本の内容を口頭で説明させる。
今日のニュースについて、自分の意見を言わせる。
→ 話す力と書く力はつながってるからだ。
2. 「書かせる」習慣を持つ
読書感想文を夏休みだけでなく、普段から小さく続ける。
日記やブログ形式で文章を書く練習をする。
→ 量を書く中でしか、書く力はつかないからだ。
3. 「書いたものにフィードバックをする」
内容ではなく、「わかりやすさ」に注目してコメントする。
「この部分はわかりにくいから、もう少し説明してみて」と伝える。
→ 「読者を意識して書く」訓練になるだろう。
まとめ
卒論が書けない学生が増えているのは、入試制度・社会環境・大学大衆化の複合的な結果だ。
文章が書けないというのは、単なる学力の不足ではなく、「考える力・伝える力」の欠如 を意味する。これは、社会に出てから最も苦労する部分でもある。
だからこそ、家庭で「話す・書く・説明する」習慣を意識的に積ませることが、
これまで以上に重要になってくるかもしれない。
なぜなら、学校任せ、大学任せでは解決できない問題だからだ。
明日は、第3回(最終回)を書きたいと思う。