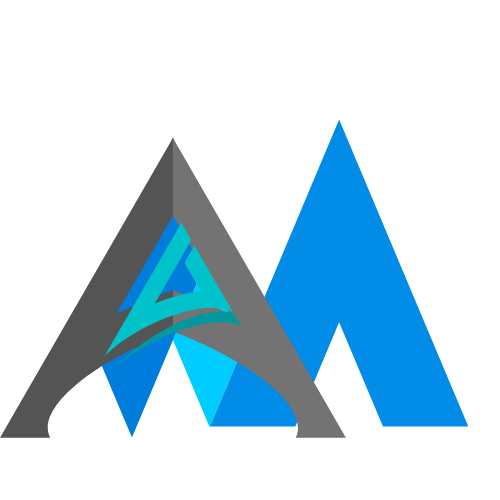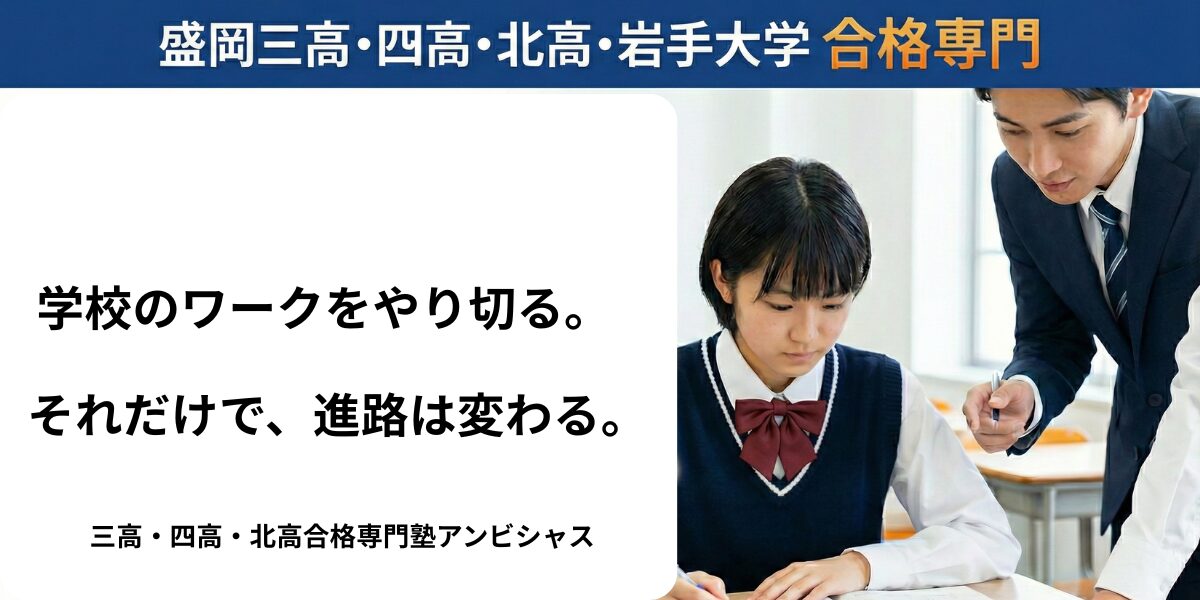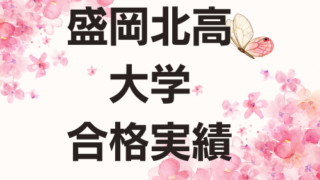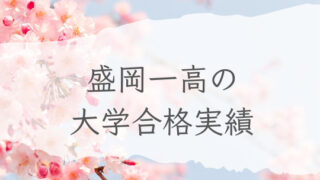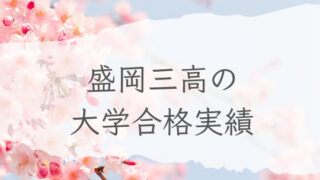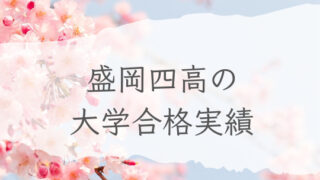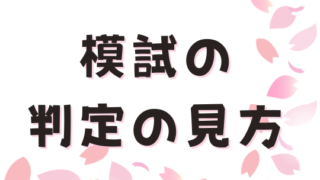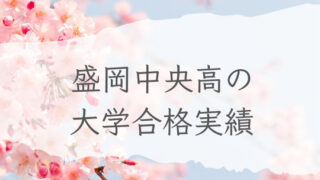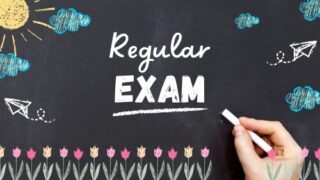今回は、子育てにおいてしばしば語られる「親と子の関係には総和の法則がある」
というテーマについて、じっくり考えてみたいと思う。
この「総和の法則」とは、
「親が子どもに関与すればするほど、子ども自身は自分で動かなくなる」
という現象を指した比喩的な言葉だ。
どうしてそんなことが起きるのか?
そして、私たち大人は子どもとどう向き合えばよいのか?
教育心理学や社会背景にも触れながら、深掘りしてみたい。
「やってあげること」が子どもの力を奪う?
こんな経験はないだろうか?
- 自分が子どもの宿題に手を出し始めたら、子どもが黙って座っているだけになった。
- テスト勉強を一緒にしたら、子どもが自分で計画を立てなくなった。
- 進路について親が調べるほど、子どもは「別に…」と無関心になった。
これはまさに、「総和の法則」が働いている例だ。
親が関与すればするほど、子どもが「自分でやる必要」を感じなくなる。
関われば関わるほど、子どもの意欲や主体性が薄れていく。
これには心理学的な裏づけもある。
「自己決定理論(Self-Determination Theory)」によると、
人間がやる気を持って行動するには、
- 自分で選んでいるという感覚(自律性)
- やればできるという感覚(有能感)
- 誰かとつながっているという感覚(関係性)
この3つが不可欠なのだそうだ。
だからこそ、親が先に全部やってしまうと、
子どもは「自分で決めた」感覚を持てなくなる。
その結果、「やる気」が失われてしまうんだ。
日本社会は“関与が愛情”という文化
では、どうして私たち親は、つい子どもに手を出してしまうのだろうか?
理由の一つは、日本社会に根付いた「手をかける親=良い親」という価値観かもしれない。
- ごはんを用意してあげる
- 塾の送迎をしてあげる
- 勉強の予定を立ててあげる
- 学校の提出物を管理してあげる
どれも「してあげること」が中心だ。
もちろん、それ自体が悪いことではない。
しかし、それが過剰になると「自分のことは自分でやる」機会を失わせてしまうのだ。
さらに、現代の親たちの頭にはこんな不安もあるだろう。
「この子が勉強しなかったら将来どうなるのか?」
「いい学校に行けなかったら、人生が大変になるのではないだろうか?」
だからこそ、つい関与を強めてしまうのだ。
しかし、それによって「動かない子」を育ててしまっているとしたら、本末転倒だと思う。
自立を育てるってどういうこと?
ここで改めて考えたいのが、「自立って何?」という問いだ。
よく「放っておく=自立を促す」と思っている人がいるが、これは大きな間違いだ。
自立とは、「自分で考え、選び、行動し、結果に責任を持てるようになること」なんだ。
子どもが自分で考える前に、親が「こうしなさい」と言ってしまえば、「考える」機会が奪われる。
失敗して学ぶ前に、親が先回りして防いでしまえば、 「責任を取る」経験ができなくなる。
つまり、親がよかれと思ってやっていることが、子どもの自立を阻むことになってしまうのだ。
「援助希求型」の関係を目指そう
では、親はどう関わればいいのだろうか?
キーワードは、「援助希求型の関係」だ。
これは、子どもが「助けて」と言ったときに、初めて手を貸すというスタンスなんだ。
助けが必要ないときは見守り、助けが必要なときに的確なサポートをする。
そのために必要なのは、「待つ力」と「信じる力」だと思う。
▼こんなふうに関わってみよう
- 子どもが質問してきたら、すぐに答えず「どこまで考えた?」と問い返す
- 「~しなさい」ではなく「どう思う?」「あなたならどうする?」と聞く
- 時間を区切って、「○時までに自分でやってみようか」と促す
- 「見てるよ」「応援してるよ」と声をかけて、安心感を与える
大切なのは、「この子ならできる」という信頼だ。
親の“成長”が、子どもの“成長”をつくる
私がこれまで見てきた中で、子どもが本当に伸びる家庭には共通点があった。
それは、親が「見守る力」を身につけているということだ。
見守るというのは、ただ黙っていることではない。
- 必要なときにだけ助ける
- 自分の不安を子どもにぶつけない
- 子どもの判断を信じて待てる
これは、親にとっても修行のようなものだ。
でも、それを乗り越えたとき、子どもは自分の力で進みはじめるんだ。
親が変わると、子どもが変わる。親が手を引くことで、子どもは前へ踏み出すんだ。
個人的には、練習でも親の送迎が必要な中学校の部活は、やりすぎだと思う。
そう。土日の練習だ。
親は、普段の練習は子どもたちに任せて、試合本番だけ見にいくのがちょうど良いんだ。
クラブチームじゃなければ、外部コーチも不要だろう。
何でも大人が関与しすぎて、子ども達だけの世界を壊してしまっていることに気がついて欲しい。
子ども達だけになった方が、自分たちで試行錯誤し始めるものなんだ。
そのせっかくの機会を妨げてしまっているんだよね。
まとめ:関わりすぎないことは、愛情の放棄ではない
最後にもう一度、「総和の法則」を振り返ってみよう。
親が100やると、子どもは0になる。
親が50で支えると、子どもは50の力を出す。
この法則は、「子どもに任せる=無関心」ではないことを教えてくれている。
本当の愛情とは、「助けたい気持ちをこらえて見守ること」かもしれない。
子どもの未来を信じ、時に手を引き、時に背中を押しながら、
一緒に「総和」の総量を増やしていく。
それこそが、親子の理想の形なのではないだろうか。