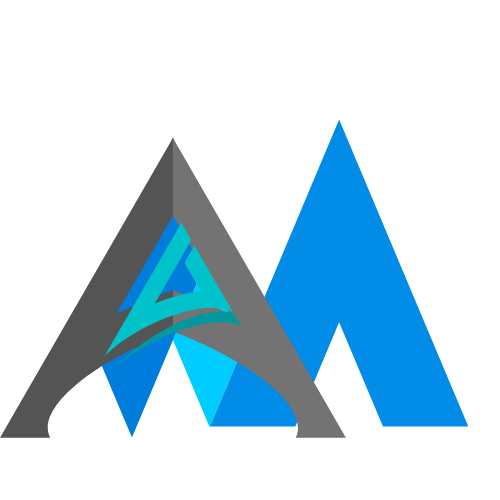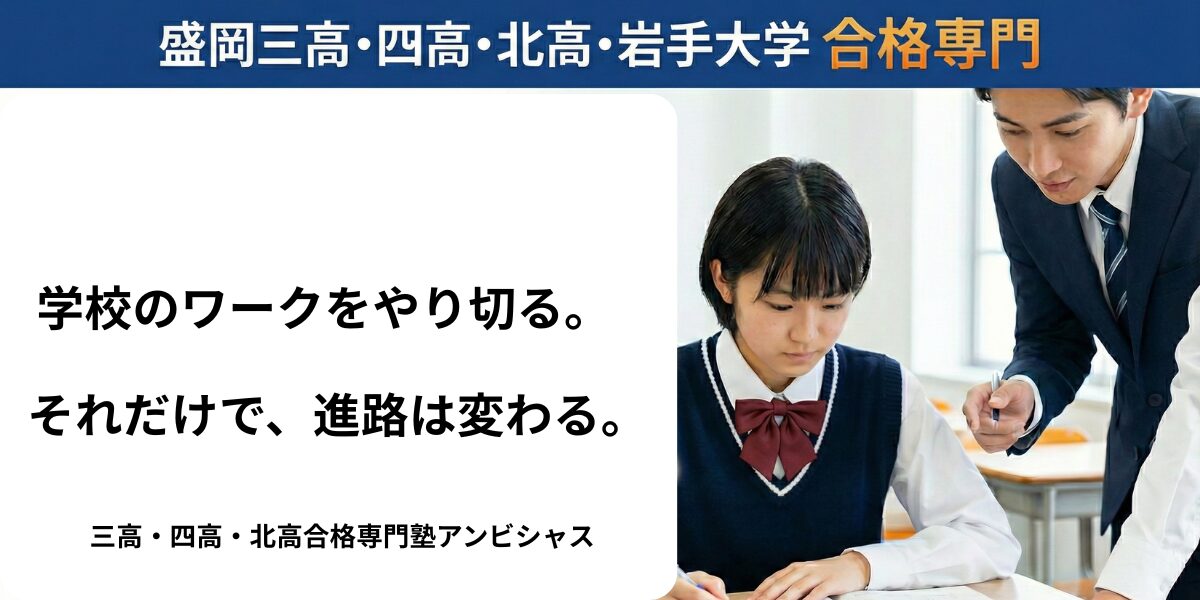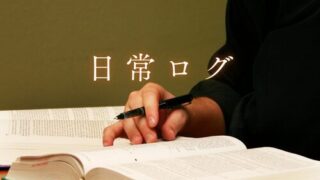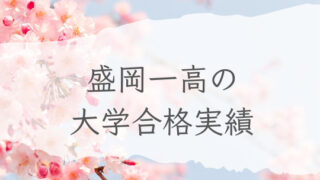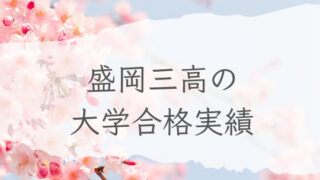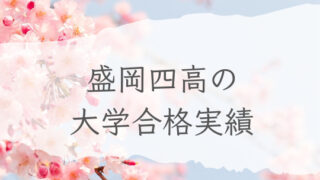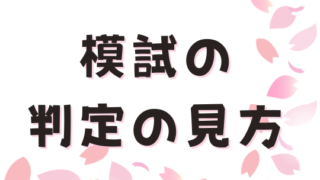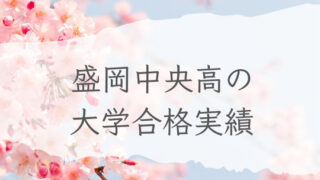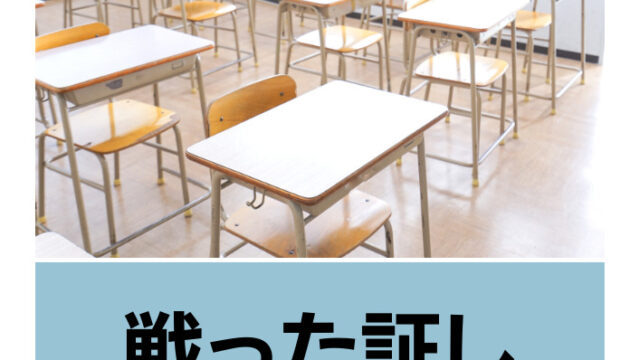勉強に慣れていない中学生や高校生が最初にぶつかる壁。
それは、「何でもかんでも取り組んでしまうこと」
結構、ありがちだなーと思う。
思うように点数が取れていない子ほど、「何でもかんでも」やろうとするんだ。
これは、一見、真面目に見えるが、いろんなことに手をつけてしまうから
全てが中途半端になってしまい、結果に跳ね返ってこないことが多い。
要は、薄まってしまうということだ。
理由は簡単で、何をどこまで取り組めばよいのかが自分では分からないから
だから、「とりあえず全部やってみよう」となってしまうのだ。
これは、「今やっている勉強は何のためにしているのか?」
ということが意識されていないということを意味する。
毎回テスト前になると慌ててしまうという人は、ほぼ、当てはまっていると思う。
同じ勉強でも、目標や目的によって
作戦(勉強量・学習内容・学習時間など)は変わるんだ。
こういうことは、スポーツに例えると分かりやすいかもしれない。
僕は柔道をやっていたから、柔道で例えてみよう。
柔道の代表的な練習に「打ち込み」と「乱取り」がある。
打ち込みは、相手に技をかけるまでを練習するものだ。
その一方で、乱取りとは簡単に言うと仮想試合を行うものだ。
技を仕上げるために打ち込みは欠かせないが、試合で技を掛けるための練習にはならない。
なぜなら、打ち込みは動かない相手に技を掛ける練習だからだ。
試合で技を掛けることができるようになるには、乱取りの数をこなさないといけない。
特に試合が近い場合はそうなんだ。
しかし、意外と、ここを意識しないで練習している人は多いと思う。
よし!
柔道での例えは、分かりづらかった笑
さてさて・・・
言いたいことは、「目標や目的を明確にしよう」ということだ。
目標なら、できれば、数字で表せる目標が良いだろう。
わかりやすい例でいえば、テストの点数や平均点との差だろうか。
このとき、自分の現在の実力と大きくかけ離れた目標を掲げるのはやめた方が良い。
良いのは、「現在の自分では届かないけれども、努力した後の自分なら取れそうな点数」
である。
目標は高すぎても、低すぎてもいけない。
目標が設定できたら、次は点数を取るためにどうするかを考えるんだ。
例えば、次のテストでの目標が80点だとしよう。
これは、100点を取る必要はないということでもある。
ここがポイントだ。
仮に、前回のテストの点数が70点だった数学を80点に上げるなら
計算や一行問題は完璧にする
少し手順が複雑な問題も自力でスピーディーに解けるようにする
ことは必要だが、
授業で扱ってない問題や、ワークの発展問題を解けるようにする
高校入試の過去問レベルを解けるようにする
ことは必要ない。
配点にもよるが、難問は「解けたらラッキー」ぐらいの感覚で構わないのだ。
優先するのは、
・計算や一行問題は完璧にする
・少し手順が複雑な問題も自力でスピーディーに解けるようにする
ことなのだ。
アレもコレもは、できない
からだ
優先順位を考えたあとは、「やらないこと」を決めよう。
例えば、英語の定期テストを構成している要素に、
「英単語」「文法」「長文」「英作文」「和訳」があるとしよう。
定期テスト1週間前に英単語を覚えることができていない人が、
英作文の練習をしても、ほとんど成果は出ないだろう。
この場合、やるべきことは「英単語」と「文法」を固めることなんだ。
もっと言うと、それ以外はやらなくていいんだ。
英単語と文法に力を注げば、その分野の点数を取れる可能性は上がるだろう。
一方で、「何でもかんでも」やろうとすると、全てが薄まり、
英単語と文法に全振りした場合よりも点数を取れない状態になりかねないんだ。
だって、スペルミスや、文法のミスでたくさん失点してしまうかもしれないからね。
確実に取れる問題を、確実に取れるように練習する
これがとても大切。あくまでテストに関しての話ね。
テストを目標にするなら
やることを絞る
やらないことを決める
これが最大のポイントだと思うよ
要は、最初から詰め込みすぎなんだ