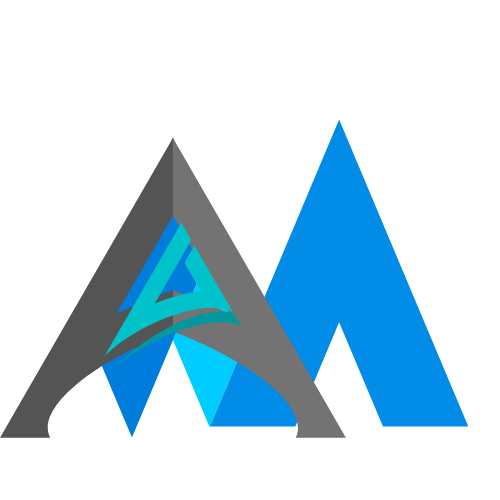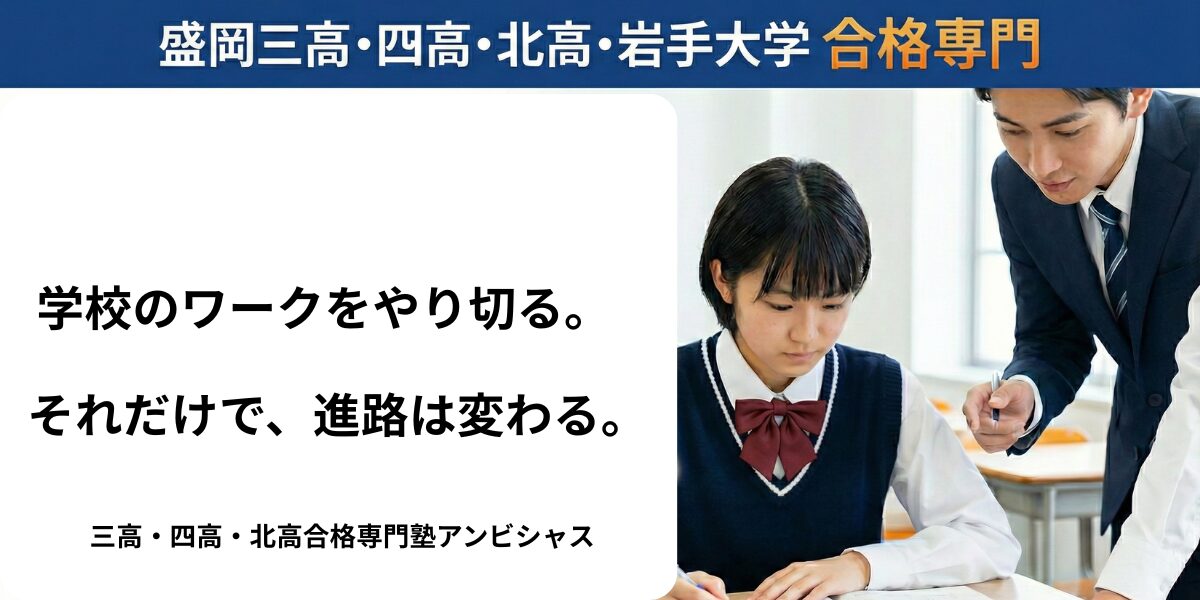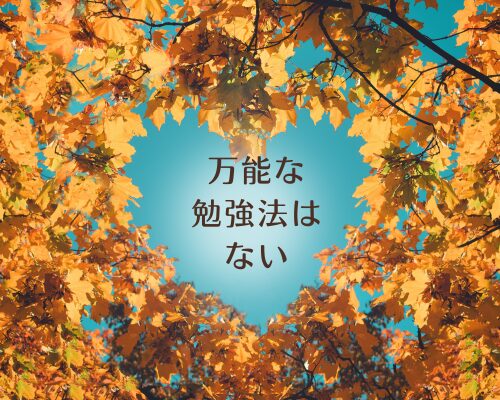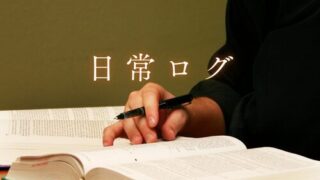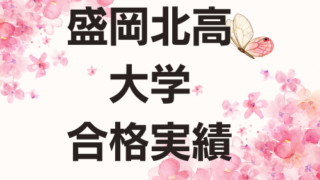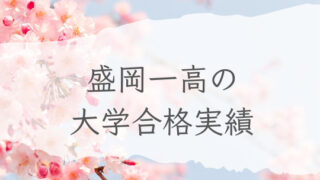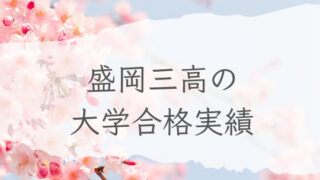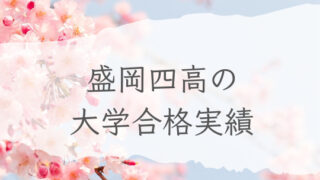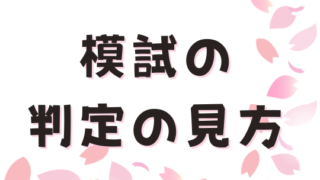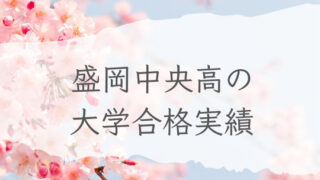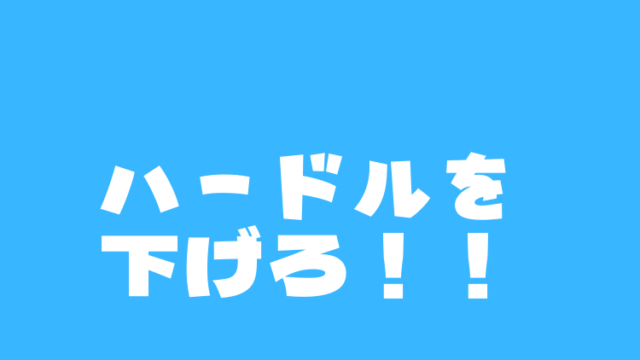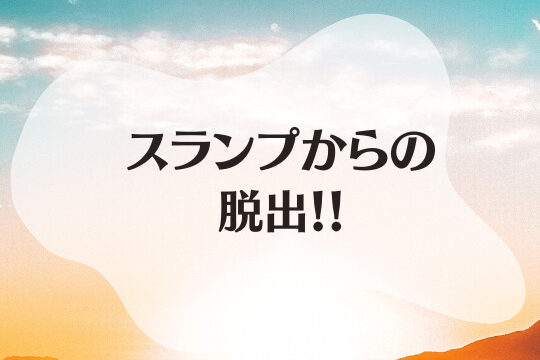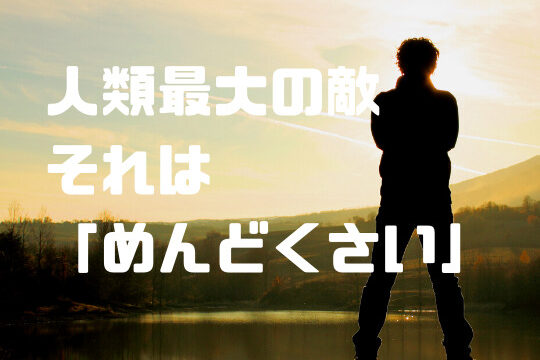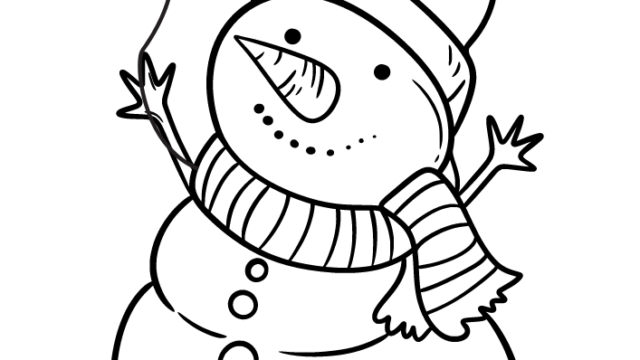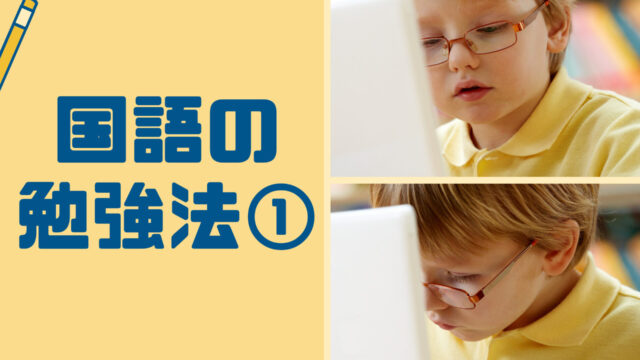塾に通うお子さんを見ていて、「一生懸命勉強しているのに、成績が思うように伸びない」「基礎を積み上げているけれど、全体として何を目指しているのか見えない」と感じる方は少なくないだろう。
教育現場でよく取り入れられる「スモールステップ学習法」は、学習を細かく分けて一歩ずつ理解を積み上げる方法だ。
基礎固めや苦手克服には非常に効果的で、「わかった!できた!」という達成感を得やすい点がメリットだ。
しかし、この方法には注意すべき欠点もある。特に「柔軟性の欠如」が指摘されることが多い。
スモールステップ学習法の落とし穴
スモールステップ学習法の最大の弱点は、決められたステップを全員に一律で適用してしまうと、学習効率が下がってしまうことだ。
具体例を挙げてみよう。
算数の分数計算に苦手意識を持つ子には、小さな段階を踏ませることで、確実に理解を深めることができる。
実際、ある中学2年生の男子生徒は、分数の計算でつまずきやすく、テストでもミスが目立っていた。そこで、スモールステップで基礎から確認する方法を取り入れた結果、少しずつ理解が定着し、「前より早く解ける!」という自信につながった。最終的には、テストで満点近くを取れるまで成長することができた。
一方、既に理解している子に同じ内容を繰り返すと、退屈さや不満につながることがある。
さらに、細かく区切りすぎると学習の全体像が見えにくくなり、「何のためにこれを学んでいるのか」という目的を見失いやすくなる点も注意が必要だ。
つまり、スモールステップ学習法は万能ではない。大切なのは、どのように使い、どう柔軟性を持たせるか、ということなんだ。
柔軟性を高めるカギは「面談」にある
ここで重要になるのが「面談」だ。
面談は単なる進路相談ではなく、お子さんの学習状況や理解度、モチベーション、家庭での勉強習慣を把握するための大切な機会だと僕は思っている。
当塾では、毎週必ず面談の時間を設け、学習状況の確認や課題の整理を行っている。
この習慣により、生徒一人ひとりの進み具合に応じて柔軟に指導内容を調整でき、基礎から応用まで無理なく学習を進めることができる。
実際、この面談だけで、大学受験をクリアしてしまう子も少なくないんだ。
面談の活用ポイント
- 進捗の可視化
面談では「前回からどれだけ成長したか」を確認する。ある中学3年生の女子生徒は、英語の長文読解が苦手だったが、毎週の面談で少しずつ成長を確認することで、達成感を得ながら自信をつけていった。「前より読めるようになった!」という小さな成功体験が、勉強を続ける原動力になったのだろう。 - モチベーションの把握
学習への意欲や不安を確認することで、学習が停滞している原因を早期に察知できる。「最近、数学が嫌になっているようです」という保護者の方からの情報にも、面談で生徒に詳しく状況を聞くことで適切に対応できるんだ。 - 学習法の改善
ノートの取り方や復習の仕方を少し変えるだけで、理解度や定着度が大きく変わることがある。あるというか、大いにある笑。ある生徒は、復習を「前日の分だけ」行っていたが、面談で「週のまとめ復習」を取り入れるよう指導したところ、テストの正答率が大幅に向上したことがあった。 - 家庭との連携
面談を通じて、家庭でも具体的なサポートが可能になる。「計算問題を1日10問解く」「毎日10分だけ英単語を復習する」といった小さな目標を、家庭で一緒に確認できることが、学習習慣の定着につながっているようだ。
保護者にできるサポート
面談で目標や課題が明確になったら、それを家庭でも共有することが大切だ。
具体的には、
- 学習時間を管理する
- 机周りを整えて集中できる環境をつくる
- 小さな達成を一緒に喜ぶ
こうしたサポートだけでも、お子さんの学習効果はぐんと高まる。ある保護者の方は、「毎晩5分だけ勉強の進み具合を話す時間を作った」と話していた。その結果、お子さんは自分の学習状況を振り返りながら進められるようになり、自然と自宅学習の習慣がついていった。そう。勉強を教える必要なんてないんだ。
まとめ
スモールステップ学習法は基礎を固めるのに優れた方法だが、そのままでは柔軟性を欠いてしまう面がある。その弱点を補うのが「面談」なんだ。当塾では毎週の面談を通じて、進捗やモチベーションを確認し、必要に応じて学習内容や進め方を調整している。さらに家庭でのサポートと連携することで、学習は単なる作業ではなく、納得感を持って進められる「成長のプロセス」へと変わっている。
お子さんの学習で大切なのは、「どれだけ柔軟に調整できるか」だ。塾と家庭が協力することで、一歩一歩の積み重ねが確かな成果につながっていくと考えている。