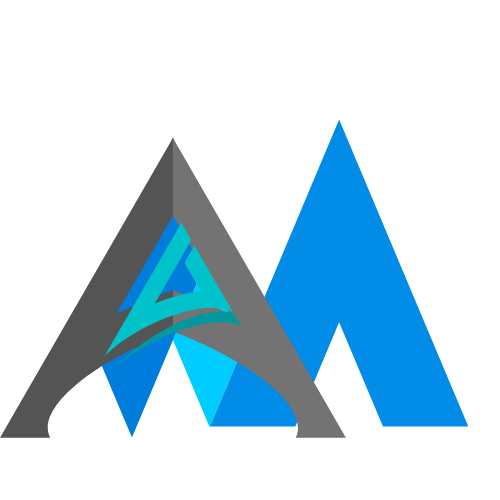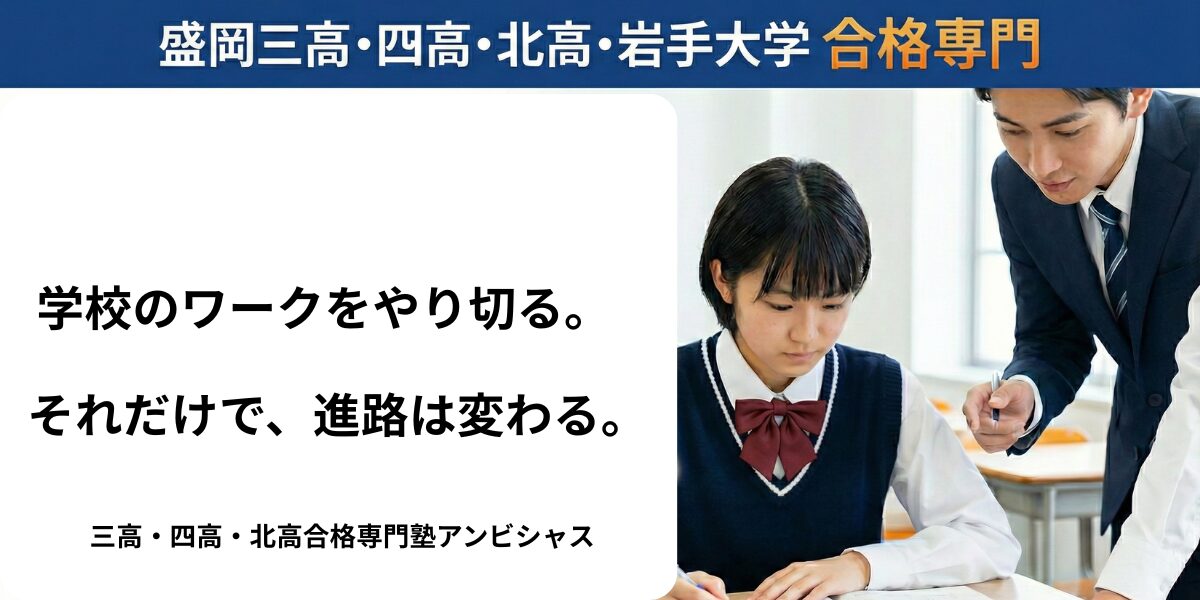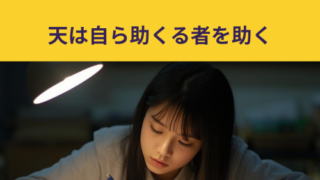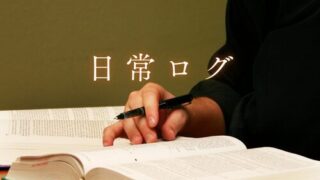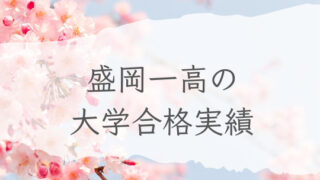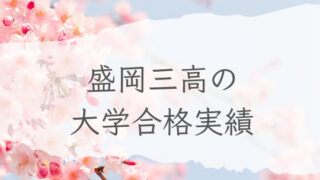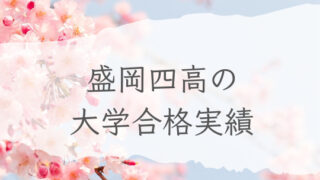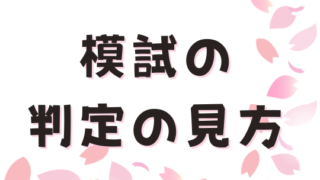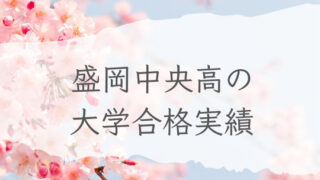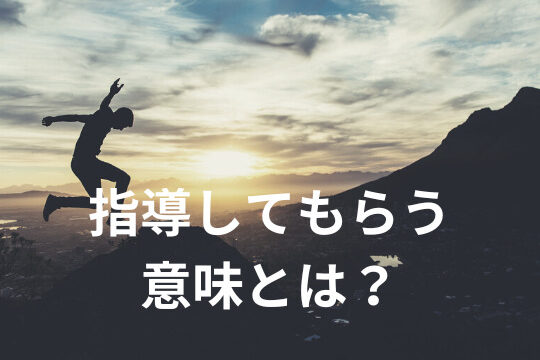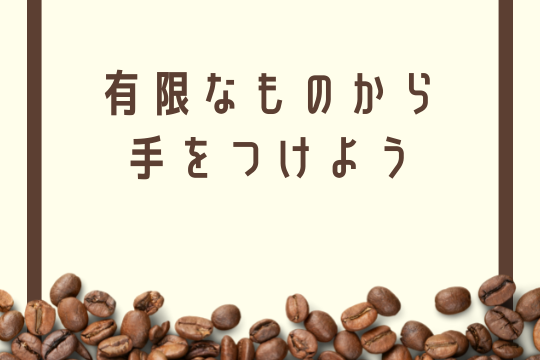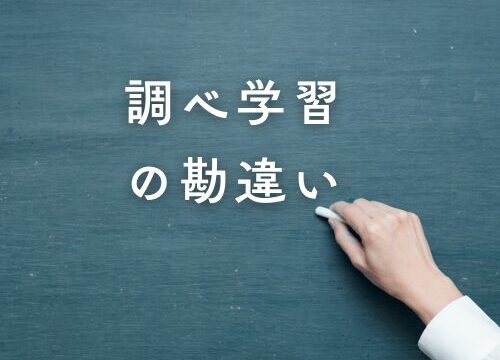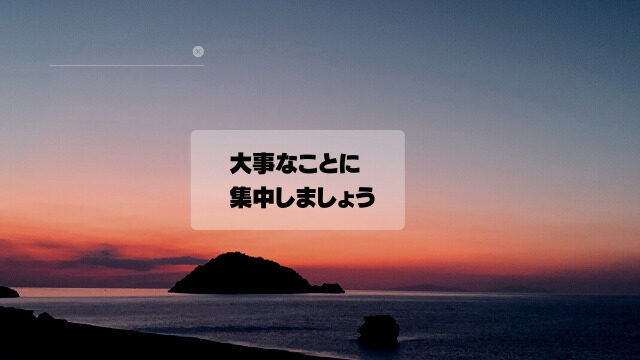中学校教育の現場では、「定期テスト廃止」の流れが一部で始まっている。
代わりに導入されているのが、単元ごとの「単元テスト」による評価だ。
これは学習の到達度を細かく評価する意図があり、
生徒一人ひとりの理解状況を正確に把握するという点では
非常に意義深い取り組みだと言えるだろう。
しかし、こうした制度の変化に対応するためには、
日々の学習のあり方を根本から見直す必要がある。
その注意点とともに、単元テスト制のメリット・デメリットを具体的に考察してみる。
今日は、硬い内容だ。時間がある時に読んでほしい。
単元テスト制とは何か?
まず、単元テスト制について簡単に説明してみよう。
従来の中学校では、学期に2回ほど行われる定期テストによって
成績を評価するのが一般的だ。
盛岡市内の中学校も、ほとんどこの形を取っている。
これに対し、単元テスト制では、
教科ごとの単元(たとえば数学なら「方程式」「関数」など)を学び終えるたびに、
その理解度を測る小規模なテストが行われる。
そして、これら複数回のテストの結果をもとに、
学期末や年度末の成績がつけられるということだ。
盛岡市内では、下橋中学校が、昨年度からこの制度を導入している。
メリット1:理解度に応じたきめ細かな評価
この制度の最大のメリットは、「理解しているかどうか」をタイムリーに測定できる点だ。
定期テストでは広範な範囲を一度に扱うため、苦手な単元がテストに含まれていない場合、
実力以上の点数がついてしまうこともある。
逆に、得意な分野が軽く扱われることで、本来の力を発揮できないこともある。
単元テストでは、各単元を学習した直後にテストが実施されるため、
学習内容が新鮮なうちに理解度を測ることができる。
これは、生徒が「わからないまま先に進んでしまう」ことを防ぐ効果もある。
つまり、学習の「つまずき」を早期に発見し、
リカバリーできる体制が整いやすくなるということだ。
メリット2:学習習慣の定着
もう一つのメリットは、学習習慣がより日常的に身につくことが期待されることだ。
定期テスト前だけ猛勉強する「一夜漬け」では、
長期的な学力向上にはつながらない(根性は身につくかもしれない)。
単元テスト制では、テストが頻繁にあるため、常に学習に対して準備しておく必要がある。
結果として、計画的に学ぶ力や、日々の授業に真剣に取り組む姿勢が培われるということが
期待されているのだ。
デメリット1:学習のペースが乱れる可能性
一方で、単元テスト制には注意すべき点もある。
まず挙げられるのが、生徒によって学習ペースが合わなくなる可能性だ。
例えば、ある単元の理解が不十分でも、カリキュラムは次の単元へと進んでいく。
そうなると、生徒は「ついていけない」という焦燥感を抱えながら、
消化不良のまま先に進むことになる。
これを防ぐためには、教師側のフォロー体制や、補習・再テストの仕組みが不可欠となる。
そうなんだ。
このフォロー体制が整っていないと、相当に厳しい仕組みなんだと思う。
デメリット2:テストに追われるストレス
また、テストの回数が増えることにより、
生徒が「常に評価されている」というプレッシャーを感じやすくなる点も否定できない。
特に真面目な性格の生徒ほど、
ひとつひとつのテストに過度な緊張や不安を覚えることがあるかもしれない。
その結果、精神的な負担が積み重なり、
学習へのモチベーションが下がってしまうことも考えられるだろう。
普段の勉強で気をつけるべき3つのポイント
では、こうした単元テスト制の中で、生徒がより良く学び、力をつけていくためには
どのような勉強の仕方が求められるのだろうか。
ここでは、特に重要な3つの点を紹介しよう。
① 授業の理解を最優先にする
単元テストは授業の内容に直結している。
よって、授業中の集中力が何よりも重要だ。
板書を写すだけで満足せず、
教師の説明を聞きながら「なぜそうなるのか」を
自分の頭で考える姿勢が必要と言えるだろう。
わからない部分はすぐに質問する習慣も必要だと思う。
② 小さな復習を日々積み重ねる
毎日の学習の中で、授業の内容を短時間でもいいので復習することが大切だ。
ノートを読み返すだけでなく、教科書の例題をもう一度解いたり、
自分なりに説明してみたりすることが大事だと思う。
単元テスト直前に焦って詰め込むのではなく、
「毎日10分」の継続が効果的だということだ。
③ 自分の理解度を自己チェックする習慣を持つ
単元テストはあくまで「確認の場」だ。
普段の勉強の中で、自分自身でも「この内容は本当にわかっているのか」
を確かめる時間を持つことが大切だ。
具体的には、簡単な問題を自作してみたり、友達と教え合ったりするのも有効だろう。
他人に説明できるというのは、その内容を深く理解している証なのだから。
おわりに
単元テストによる成績評価は、時代の要請に応じた新しい学習のかたちだ。
それは「テストのための勉強」から、「日々の理解と定着を重視する学び」への転換
を促すものでもある。
ただし、制度が変われば、それに対応した学び方もまた問われるということだ。
テストの頻度が高まる中で、何を優先し、どんな習慣を身につけていくのか。
それを見極めながら、地に足のついた学びを実現していくことが、
これからの中学生には求められていると言えるだろう。